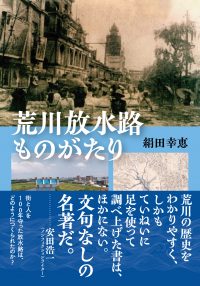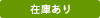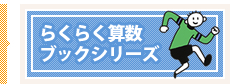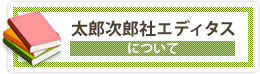荒川放水路ものがたり
荒川放水路ものがたり
| 発行日 |
2025年10月発行 |
| 判型 |
A5判・上製 |
| 頁数 |
272ページ |
| 価格 |
本体3000円+税 |
| ISBN |
ISBN978-4-8118-0869-7 |
| Cコード |
0021 |
安田浩一さん(ノンフィクションライター)推薦!
「荒川の歴史をわかりやすく、しかもていねいに足を使って調べ上げた書は、ほかにない。文句なしの名著だ。」
利根川東遷・荒川西遷工事により、江戸の大動脈となった荒川(隅田川・大川)。大きな繁栄をもたらしたいっぽうで、毎年のように洪水で多数の犠牲者を出す暴れ川でもあった。明治末の大洪水を契機に、人と街を守るため24kmの大放水路が計画される。19町村の1300戸にふってわいた立ち退き、工事をめぐる軋轢、そして震災。
教え子の疑問に触発された著者が、20年ちかくにわたって地域の生き証人から聞き歩き、資料を渉猟して再現した人と川のものがたり。

まえがき
1 荒川の歴史
1 荒川のすがた
2 利根川・荒川の移り変わり
3 荒川のおもな洪水
4 熊谷堤
2 明治末期の大洪水
1 明治40年の大洪水
床の上でさざ波/住民が堤の上でにらみ合い
2 明治43年の大洪水/
圦を閉じて炊き出しを/洪水を知らせる寺々の鐘
飲み水をもらいに舟で/流されていく家
平方電報/農業用の舟で逃げる
千住の町と天皇の勅使/電話を堤の桜につるす
軍も出動した向島・本所・深川/農家は種籾さえもなく
免租の願いと炊き出しの報告
3 荒川放水路開削が決まるまで
1 東京市議会・帝国議会でのようす
2 放水路の位置と陳情書
3 内務省の放水路計画
4 用地買収から立ちのきへ
1 千住土地収用所のはたらき
2 江北村
江北村の調査と買収/水場は安く買収された
墓もいっしょに越した
3 西新井村
とりあえず立ちのく/通帳を見ては嘆いた
4 千住の北をまわって
千住元宿の人たちと感旧碑/川底の地図
流れの下になった家/伊興は土地が高いから
24戸の村に20戸の移転/神社も移転
移転は第一次世界大戦の年/農民の心情は
移転して分教場に
5 葛飾・墨田あたり
編入されたりなくなったりした村/コロで引いてきた家
買収ときいて寝込んでしまった/消えた木下小学校
立ちのいた宝蔵寺/「寺の前」の家も立ちのく
立ちのいた牛たち/「役場の家」の移転
木下川薬師の場合/上木下川の村と立ちのき
万福寺と下木下川の村/白髭神社
6 一路海へ
消えた江戸川の平井小学校・松川小学校/千葉街道の四股
最後は何もなくなって/農業をあきらめて大工に
老婆の述懐/最後の立ちのき/裁判のその後
5 工事と人びとのくらし
1 荒川放水路工事
2 流域の人びとと放水路工事
少年の目にうつった工事/ドロ汽車の煙で焼けた農家
本木圦/交通を遮断しないで下さい
宮城・小台からの通学/事故にあった人たち
放水路の生き物/文明の灯は二つの川を越えて
ジャリと交換した昼飯/命からがらの行列と土手
土手の仕上げと低地の埋め立て/ゆれる浮き橋
管理人の川門さん/千住機械工場と仮船溜
トロッコと機関庫と子どもたち/エキスカの響
遠くなった駅/工事で働いた人びとと一日の賃金
震災のときの旧四つ木橋あたり/震災のあとの土手や河川敷
小松川橋とエピソード/放水路下流の水運と閘門
村の分離統合/岩淵水門上流の買収と工事
6 荒川放水路と青山士氏
講演・荒川改修工事に就いて/青山士氏の歩いた道
7 荒川放水路ができあがる
通水式と小さな記念碑/土手の高さ
8 荒川放水路とあゆむ
放水路にできた渡し/子どもの天地
放水路の夏/河川敷に下りた飛行機
土手の草を軍馬のえさに/河川敷にチューリップ
空襲と青空教室/荒川は炎の川であった
食料不足と河川敷の耕作/荒川飛行場と足立第八中学校
河川敷の連合運動会など/その後の大水害
さびれる水運と閘門/草刈の碑
新四つ木橋架橋中の事故/旧四つ木橋下手の試掘
釣り船屋の四季/荒川放水路の花火
あとがき
年表
補章 絹田幸恵さんのことと、その後の荒川放水路(長谷川敦)
1 絹田幸恵さんのこと
『足立史談』での連載/地味派手な人/パーキンソン病に倒れる
2 その後の荒川放水路
放水路ではなく放臭路/川はよみがえったか
令和元年東日本台風も持ちこたえた/流域治水で荒川を守る
参考文献・展示施設案内

1930年、朝鮮に生まれる。家族は2歳のときに岡山県に帰郷。1950年岡山大学教育学部を卒業、小学校教員となる。1957年上京、東京・足立区で教員となる。
1972年ごろから、地域を歩いて住民の話を聞き、工事事務所などをたずね、荒川放水路の歴史を授業にしてきた。1988年に教員を退職後、これまでの調査をまとめ、『荒川放水路物語』(1990年、新草出版)として出版。本作により平成3年土木学会・出版文化賞を受賞。1992年にパーキンソン病を発症、闘病生活に入る。2008年、肺炎により死去。